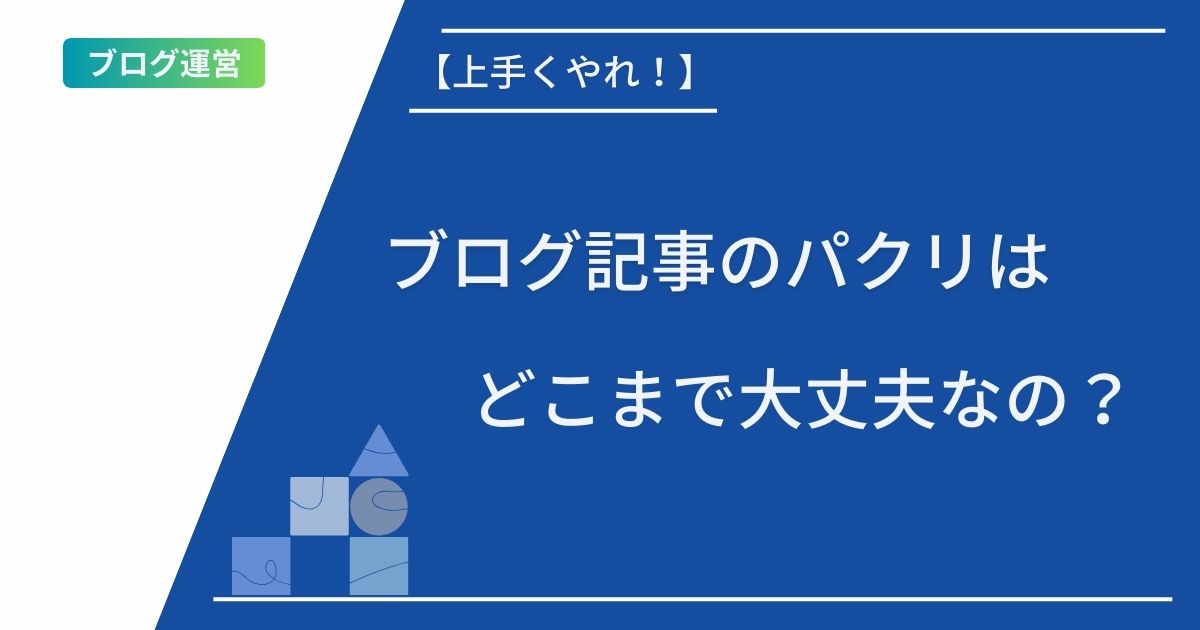今回は

他のブログを真似ろって言うけどなぁ…。
そんな悩みを解決していきます。
- ブログ初心者さん
- パクリ記事のNGラインが知りたい人
- 他のサイトを真似ることに抵抗のある人


よくビジネスの世界では「成功してる人の真似をしろ!」なんて言われますよね。
ブログも一緒です!
でも、「本当に真似なんてしていいのかなぁ…」と不安になる気持ちもわかります。
そこで本記事では、ブログ記事を執筆する際「他人の記事内容をパクって大丈夫なのか?」といった疑問について一緒に深掘りしていきましょう。
先に結論からお伝えしておくと、
過度に真似た記事は「パクリ」と呼ばれてしまう恐れがあるのでおすすめしません。
また、違反にならないための適切な引用の方法や、オリジナリティを保つためのアイデアについても解説していくので、ぜひ最後までお付き合いください。
それでは、本題に参ります。
他人の記事を丸パクリ(完全コピー)するのは絶対NG


Web上において、他人が作成した記事を無断でコピーし、自身のサイトやブログに掲載する行為は著作権違反にあたります。
作者の承諾なく、その成果を自己のものとして使用することは、法律で厳しく禁じられているので覚えておきましょう。
「著作者」について詳しくは⇩
著作者とは、「著作物を創作する者」のことです(第 2 条第 1 項第 2 号)。小説家や
引用元:文化庁
画家、作曲家などの「創作活動を職業とする人」に関わらず、作文・レポートなど
を書いたり、絵を描いたりすれば、創作した時点でその人が著作者になります。上手
いか下手かということや、芸術的な価値などといったこととは、一切関係ありません。
経済的な価値を伴って利用されないと意識しづらいかもしれませんが、手紙やスマ
ートフォンで撮影した写真など、私たちが日常生活で作成したものも、定義さえ満た
せば著作物となるのです。
著作権法が保護するのは
- テキスト
- 写真
- イラスト
など、創作性を有するあらゆる作品になります。
これに違反した場合、法的措置を取られる恐れがあるため、リスクは非常に大きいです。
下記の方はYouTubeの事例ですが、損害賠償の責任を負うことにもなりかねません。
他人のブログ記事をコピーすることは、短期的に見れば労力を削減することになるかもしれません。
ですが、長期的に見ると、



ユーザーや検索エンジンからの評価を下げる原因となってしまいます。
オリジナルのコンテンツを制作することで、ユーザーにとっても価値のある情報源となり、訪問者の満足度やリピーターの増加に繋げていきましょう。
正当な引用や再構築など法に基づく適切な方法を用いて、創意工夫を凝らした記事作成に務めることが大切です。
オリジナリティのあるコンテンツは、長い目で見てサイトの成長に大きく繋がっていきます。
パクリ記事のNGラインは?


ブログの記事作成においては、オリジナリティが重視されます。
他人の作品を模倣することなく、



独自の視点や新しい情報を提供すること。
一次情報の集め方について詳しくは、下記の記事をご覧ください。
でも、どこまでがオリジナルで、どこからがパクリ(盗用)にあたるのか、その境界線は曖昧なのも事実です。
そこで、次の3つのNGラインを深堀りしていきたいと思います。
- 記事内容のコピペ
- 語尾だけを変える
- 画像を無断で使う
順番にみていきましょう。
記事内容のコピペはNG
当然ですが、
文章のコピー&ペーストは、著作権法の侵害に当たります。
たとえば、他者のブログ記事をまるごとコピーして自分のブログ記事に載せる行為は明確な違反行為です。
著作権のある著作物を、著作権者の許諾を得ないで無断で利用したり、自分が創った著作物だと騙して利用すると著作権侵害となります。
引用元:公益社団法人著作権情報センター
最悪、訴えられて、損害賠償を請求されたりするなどのリスクを負うことになるので、他人のブログ記事をコピペする行為はNGだと覚えておきましょう。



完全コピーの記事は、完全にアウトです!
語尾だけ変えるのもNG
文章の盗用として、語尾を変更する程度の微細な編集もNGです。
本質的には他人のアイデアや構成を流用しており、これは独自性にかける行為とされます。
ユーザーは新鮮でユニークな視点を求めており、見かけ上の変更では満足しません。
心から価値を感じ取れる記事は、徹底的なリサーチと創造的な思考から生み出されます。
結局のところ、ユーザーにとって有意義なコンテンツは、真摯な努力の結晶だと覚えておきましょう。
画像を無断で使うのもNG
執筆だけでなく、画像の取り扱いにも注意が必要です。
特に、
インターネットから無断で画像をダウンロードし、その画像を記事に使用することは著作権の侵害となります。
私的な使用であっても、画像にはそれを作成した者の権利が存在します。
記事に画像を使用する場合は、



フリー素材のサイトを利用しましょう。
また、独自の画像を作成することで、記事に説得力を加えることができます。
記事を「パクる」のではなく「参考」にする


他の記事を見て感銘を受けたとき、その情報を「パクる」のではなく、「参考」にして独自の価値を生み出すことが大切です。
独創性をもって創造することで、ユーザーに新しい発見やインスピレーションを提供することが可能になります。
最初は難しいと思うので、下記のことを試してみましょう。
- 記事構成を参考にする
- 必ず自分の言葉で書く
- 参考にした記事を超える内容にする
詳しく解説していきます。
記事構成を参考にする
良い記事と出会った際には、



構成を参考にすることから始めましょう。
ポイントは、順序立てて情報が展開されている流れを理解することです。
例えば、リード文で興味をひきつけ、本文で詳細情報を提供し、結論(まとめ)で締めくくるという記事全体の流れですね。
自分の記事にもこのような流れを取り入れることで、ユーザーが論理的かつスムーズに情報を理解できるようになります。
また、構成要素を参考にしながら、それに独自の解釈を加え、リストアップされた情報を更に展開させるなど、単に模倣するのではなく、改善を重ねることが重要です。
自分の言葉で書く
記事を参考にする際は、自分の言葉で書くことが絶対条件です。
自分自身で情報をインプットして、理解を深めなければ「オリジナルの発信」はできません。
それにより、他者と区別する個性が反映された内容が生み出されることになるでしょう。
文章を書くときには、



常に独自の視点や感情を取り入れてください。
書くべきことを、読み手に対しても配慮しながら自然体で表現することが大切です。
そうすることで、同じ情報を扱っていても、ユーザーに新鮮な気持ちで読んでもらえる記事を作成できるようになります。
参考にした記事を超える内容にする
参考となる記事がある場合、その記事にコンテンツを足すのではなく、1歩進んだ内容にする努力が求められます。
これは、追加された情報や独創性が、ユーザーにとっての価値を高めるためです。
個別の事例やデータ、独自の見解などを取り入れて、充実した内容にしていくことがポイントになります。
とりわけ重要なのは、



その分野の最新情報を取り入れて、記事の鮮度を保つことです。
ユーザーにとって有益な、新しい情報を提供することで、参考にした記事を超える価値をもたらすことができるでしょう。
ブログ記事の「引用」ルール


ブログ記事を書く際、他者の言葉やアイデアを用いること「引用」と言います。
しかしながら、引用は適切な手順を踏まないと、著作権の侵害や信頼性の失墜に繋がりかねません。
引用には基本的なルールが存在します。
重要なので、



覚えておいて下さい↓
① 引用部分が明示されていること(明瞭区別性)
引用元:https://www.gmosign.com/media/tokushu/tyosakuken/
② 引用元が明示されていること
③ 自分の著作部分と引用する著作物との主従関係が明確であること(附従性)
④ 他人の著作物を引用する必然性があること(必然性)
⑤ 引用部分を改変していないこと
倫理的な観点を鑑み、引用はあくまで補助的な要素とするべきです。
オリジナリティを保ちつつ、引用することで自記事の信憑性を高められるよう心がけましょう。
引用する量にも気を配り、元のコンテンツの価値を損なわない範囲に留めることが重要です。
これらの規則を守ることは、著作者を尊重し自分自身の信頼性を維持する上で、不可欠です。
適正な引用を行うことでユーザーに有益な情報を提供すると共に、知的財産権の尊重という法的・倫理的責任を全うすることにも繋がります。
正しく記事を作成するためにも、これらのルールを誠実に遵守しましょう。
記事の作成が難しいなら「AIツール」がおすすめ


パクリ記事の境界線に怯えるくらいなら、AIを使って記事作成に取り組んでみましょう。
ブログを効率よく運用したい方には、



「AIツール」は必須ですね。
コンテンツ作成の時間短縮はもちろん、アイデア出しから文章校正まで、幅広い役割を担ってくれます。
キーボードに向かう作業が負担であれば、AIの力を借りると良いでしょう。
AIライティングツール
AIライティングツールとは、人工知能を活用してテキストコンテンツを生成するソフトウェアのことです。
このツールはデータを解析し、文法的に正しいだけでなく、自然な文章を作り出す能力も備わっています。
例えば、提供されたキーワードやトピックから適切な「タイトル」や「本文」、「見出し」を作成してくます。
この提案をもとに記事を構成するため、構想に悩む時間が削減され、より効率的に作業が進むでしょう。
文章生成のみならず、校正や言い回しのバリエーション提案など、クリエイティブな部分の支援も期待できるのです。
当サイトが使用するのは「ラクリン」
「ラクリン
ChatGPTを搭載したAIライティングツールの1つであり、ブログの記事作成に特化したAIツールのことです。
このツール最大の魅力は、キーワードを入力するだけで質の高い記事が短時間で出来上がる点にあります。
当サイトの他にも、



多くのブロガーさんが使ってますよ↓
さらには言葉遣いやスタイルも指定できるので、自分のブログのトーンに合わせた文章の作成も可能です。
手間と時間をかけずに質の高いブログを運営するサポートが受けられるため、ブログ初心者でも簡単に使うことができます。
詳しい解説は、下記の記事を参考にして下さい。
ブログの記事をパクられたら


まず、自己のブログのコンテンツが無断で使用されている事例に遭遇した場合、冷静に対処を始めることが重要です。
対応策としては、最初にコピーされた記事の存在を確認し、スクリーンショットなどの形で証拠を確保します。
次に、



無断使用している側に連絡を取ってください。
この際、訴える前に柔らかい表現を用いて、権利侵害であることを友好的に伝えることが肝心です。
たとえば「貴サイトに掲載されている私の記事の内容が許可なく使用されているようです。早急に削除いただけますでしょうか?」といったメッセージが良いでしょう。
大切なことは、対話を試みる際も、権利を主張する際も、敵対的な姿勢よりも協調的な態度を保つことです。
もし話し合いで問題が解決しない場合は、権利保護のためにGoogleに連絡を行います。
Googleは著作権侵害に対して取り組んでおり、適切な報告を行えば対処してくれるでしょう。
「著作権侵害の報告」ページがあるのでそちらに連絡すればOKです。
このように、自分のブログ記事が無断転用されたことを知った際は、落ち着いて証拠を集め、まずは相手に連絡を取り、和解を目指しましょう。
その上でうまくいかない場合は、冷静にGoogleなどの関連機関に報告して対処を求めるのが適切です。
まとめ:ブログ記事のパクリはどこまで?


ブログの記事は、最終的に自分の言葉で創造的に書くことが大切です。
他人の作品を無断でコピーすることは権利侵害に該当し、信頼を失う原因となります。
そのため、記事を参考にする際は情報の構成をヒントにし、独自の視点で「潜在的なニーズ」まで深堀りしましょう。
独自性のある記事作りは、



ユーザーにとっても価値があるものになります。
副業でのブログ運営は継続が鍵となるので、焦らずに正当な方法で魅力ある記事を目指しましょう!
ブログ記事に載せてはいけないことについては、下記の記事で詳しく解説してあります。
お立ち寄りください⇩
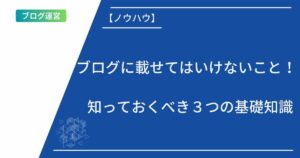
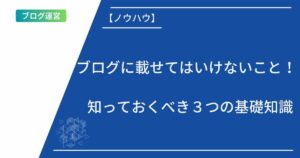
以上、最後までお付き合いありがとうございました。